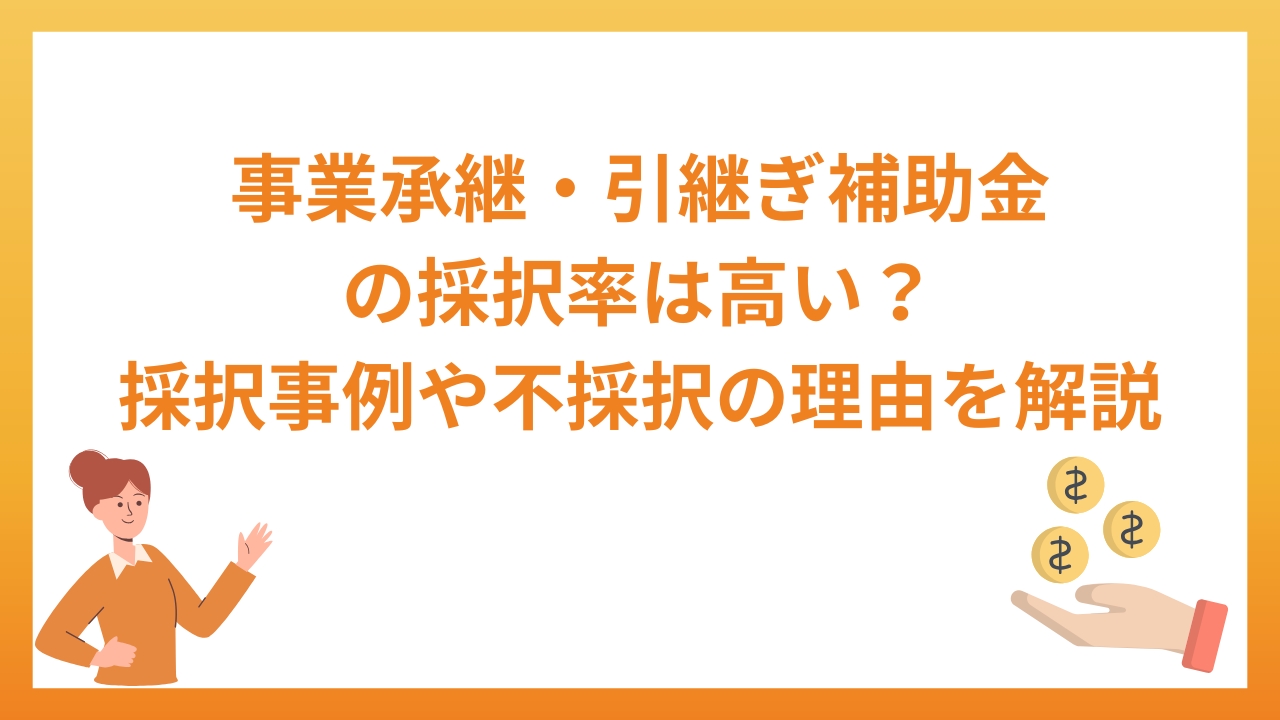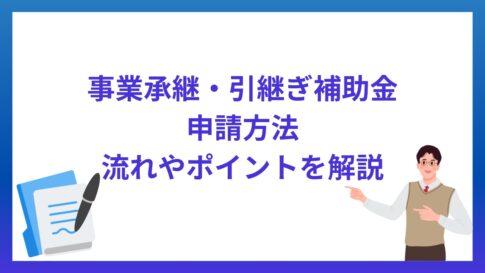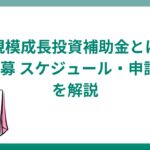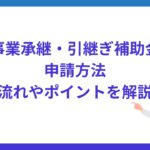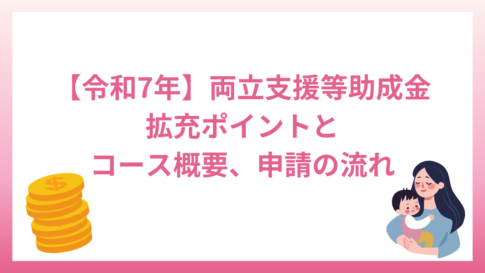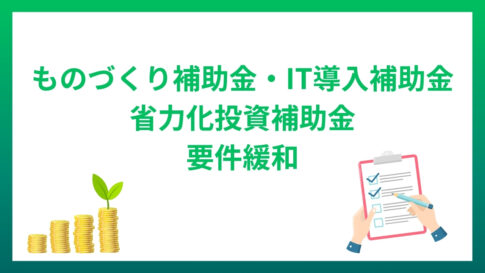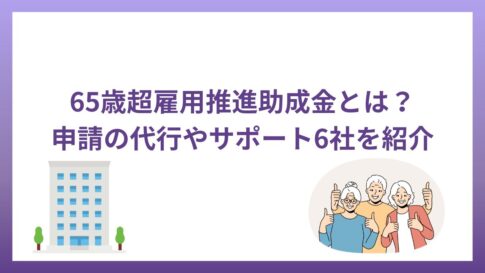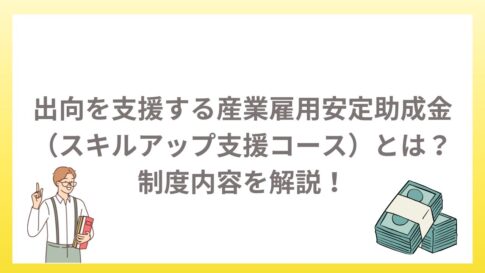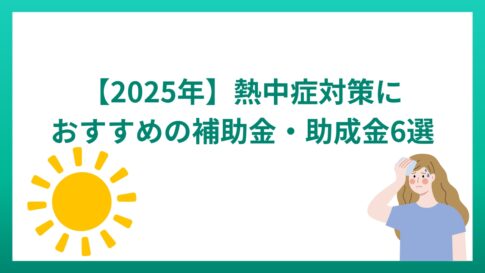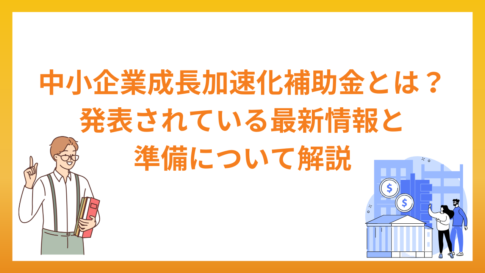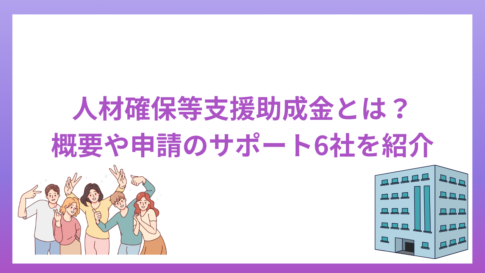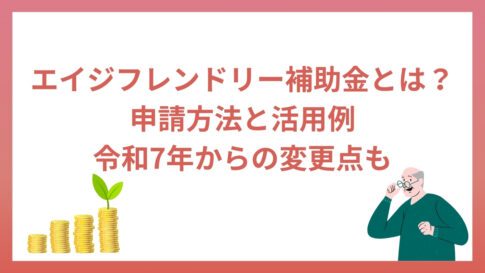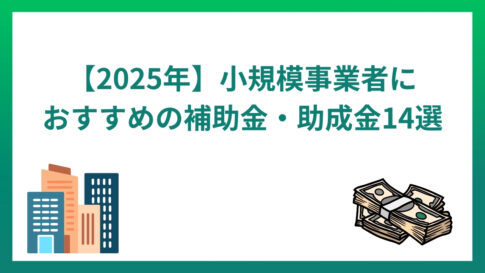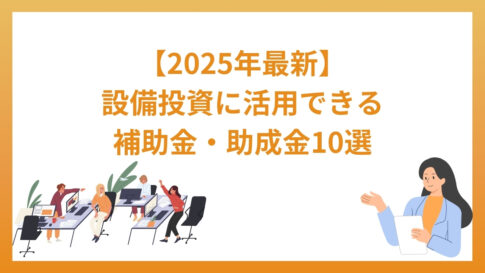事業承継・引継ぎ補助金を申請するにあたり、多くの人が気になる項目は、採択率ではないでしょうか。
採択率を確認することで、自社が補助金を受け取れるかどうかの判断材料にできます。
今回は、発表されているデータをもとに採択率を計算し、採択された事例や不採択の理由について解説します。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度は?
事業承継・引継ぎ補助金の概要
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業や小規模事業者が事業承継やM&Aを契機に行う経営革新等の取り組みに対し、必要な経費の一部を補助する制度です。
補助枠は「経営革新枠」「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」の3つに分かれ、最大800万円の補助が受けられます。
公募要領に沿って事前準備、申請を進め、採択後は事業を実施、実績報告を経て補助金が交付される仕組みです。
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は公募回によって異なる
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は、公募のたびに変動しています。
公募回ごとの採択率
過去の公募回ごとに全体採択率をまとめると、以下のとおりです。
| 公募回 | 採択率 | 申請者数(件) | 採択者数(件) |
|---|---|---|---|
| 1次 | 51.40% | 1033 | 531 |
| 2次 | 55.15% | 631 | 348 |
| 3次 | 56.55% | 626 | 354 |
| 4次 | 55.06% | 810 | 446 |
| 5次 | 59.82% | 799 | 478 |
| 6次 | 60.67% | 862 | 523 |
| 7次 | 59.48% | 839 | 499 |
| 8次 | 60.55% | 730 | 442 |
| 9次 | 61.20% | 853 | 522 |
| 10次 | 61.03% | 526 | 321 |
参考:採択結果(令和3年)、採択結果(令和4年)、採択結果(令和5年)
採択率の目安といえる数字は予想できますが、具体的に採択率が固定されているわけではありません。
概ね、50%~60%であると取られておいて差し支えないでしょう。
申請枠別の採択率
事業承継・引継ぎ補助金には複数の申請枠があり、それぞれの枠によって採択率にも違いがあります。
| 公募回 | 項目 | 経営革新 | 専門家活用 | 廃業・再チャレンジ |
| 1次 | 採択率 | 50.24% | 51.52% | 55.88% |
| 申請者数 | 209 | 790 | 34 | |
| 採択者数 | 105 | 407 | 19 | |
| 2次 | 採択率 | 55.85% | 55.45% | 42.86% |
| 申請者数 | 188 | 422 | 21 | |
| 採択者数 | 105 | 234 | 9 | |
| 3次 | 採択率 | 56.61% | 57.35% | 44.83% |
| 申請者数 | 189 | 408 | 29 | |
| 採択者数 | 107 | 234 | 13 | |
| 4次 | 採択率 | 55.30% | 55.98% | 35.71% |
| 申請者数 | 264 | 518 | 28 | |
| 採択者数 | 146 | 290 | 10 | |
| 5次 | 採択率 | 60.19% | 60.71% | 45.95% |
| 申請者数 | 309 | 453 | 37 | |
| 採択者数 | 186 | 275 | 17 | |
| 6次 | 採択率 | 61.06% | 60.26% | 62.16% |
| 申請者数 | 357 | 468 | 37 | |
| 採択者数 | 218 | 282 | 23 | |
| 7次 | 採択率 | 60.70% | 60.04% | 35.71% |
| 申請者数 | 313 | 498 | 28 | |
| 採択者数 | 190 | 299 | 10 | |
| 8次 | 採択率 | 60.18% | 61.23% | 54.55% |
| 申請者数 | 334 | 374 | 22 | |
| 採択者数 | 201 | 229 | 12 | |
| 9次 | 採択率 | 60.05% | 62.50% | 56.00% |
| 申請者数 | 388 | 440 | 25 | |
| 採択者数 | 233 | 275 | 14 | |
| 10次 | 採択率 | 募集なし | 61.39% | 37.50% |
| 申請者数 | 募集なし | 518 | 8 | |
| 採択者数 | 募集なし | 318 | 3 |
各枠に科せられる条件や審査の観点が異なるため、採択率にも差が出ます。
採択率は高めであるが「容易」であるわけではない
事業承継・引継ぎ補助金の採択率について「高い」と感じる人もいるでしょう。
しかし、採択率が高いからといって、容易に受給できる補助金であると考えることは大きな誤りです。
概要で解説したとおり、申請にあたっては認定経営革新等支援機関からの支援を受けなければなりません。
計画書には専門家の意見を踏まえる必要があり、専門家のサポートを受けた万全な状態で申請している状況です。
それにもかかわらず、採択率は概ね50%台であり、申請にかかる労力を考慮すると決して容易ではありません。
事業承継・引継ぎ補助金の採択事例
過去の採択事例を参考にすることで、どのような事業計画や活用方法が補助金の対象として認められやすいのか、イメージしやすくなります。
経営革新:創業支援類型
- サブスクリプション型のお弁当プラットフォーム事業の新展開
- 飲⾷店のIoT導⼊に伴う効率的な飲⾷事業の新設
- 地元食材を活用したハンバーガーテイクアウト事業
経営革新:経営者交代類型
- 神⼾市北部と周辺地域にて⾼齢農家に向けて農作業代⾏事業の開始
- 縫製⽤ミシン導⼊に伴った受注増に対応するための業務効率化
- 生成AIを活用した人材スカウトメール作成支援サービスの開始
経営革新:M&A類型
- 地域課題へ取り組む、学習塾が運営するフリースクール事業の展開
- 製造業から小売業へカスタマー向けテイクアウト事業の新設
- 酒蔵インバウンド事業、および、清酒製造受託事業の新設
専門家活用や廃業・再チャレンジの事例公開はなし
専門家活用や廃業・再チャレンジは、申請件数や採択件数のみ公開されています。
具体的な活用の中身は公開されておらず、参照できる情報がありせん。
公募要領をよく理解し、自社の計画が採択要件を満たしているか、慎重に確認しましょう。
【参考】事業継承・引き継ぎ補助金|事業承継・M&A補助金事務局
事業承継・引継ぎ補助金で不採択になる理由
事業承継・引継ぎ補助金で不採択になってしまう理由はいくつか考えられます。
その中でも代表的なものは、以下のとおりです。
対象の事業者ではない
補助対象の事業者でない限り、計画内容に問題がなかったとしても採択されることはありません。
対象事業者であることが大前提と考えましょう。
たとえば、事業承継・引継ぎ補助金では、以下のように対象事業者が定められています。
- 国内で事業を営んでいること
- 地域経済の発展に貢献していること
- 法令遵守上の問題を抱えていないこと
対象外であるにもかかわらず申請すると、漏れなく不採択となってしまいます。
また、申請に要する時間やコストが無駄になってしまうため、必ず事前の確認が必要です。
事業承継の要件を満たせていない
事業を引き渡せば「事業承継」とみなされるわけではなく、株式の譲渡割合などいくつもの要件があります。
これらの要件を満たせていないと、事業を引き渡す計画でも事業承継・引継ぎ補助金では採択されません。
支援機関が計画を作成すると、この点も考慮されているはずですが、見落としていると不採択になってしまいます。
補助金事業の要件に該当していない
補助金では「どのような取り組みを支援するか」が応募要項に明記されています。
これに合致した取り組みを計画し、文書化して提出しなければ、採択の対象となりません。
もちろん、要件に沿っていたとしても審査で採択されない可能性はあります。
しかし、要件に合致していない場合は、そもそも審査の対象外となるため、細かい部分まで公募要領を確認する作業が重要です。
提出書類に不足など不備があった
申請書類に不備がある場合も、不採択になる可能性があります。
申請は「jGrants」と呼ばれるオンラインシステムを通じて実施するため、案内に目を通しておきましょう。
必要な書類がすべて揃っているか、記載内容に間違いや抜けがないかを事前にチェックすることが重要です。
なお、書類の不備に関しては、事務局側から連絡を受けられる場合があります。
期限内に修正対応ができれば、即時不採択にはならず、審査対象として進めてもらうことが可能です。
【参考】jGrants|デジタル庁
事業計画書の内容が十分でない
審査では、事業計画書の内容が重要視されると予想されるため、説得力があり魅力的な内容を作成することが求められます。
計画書の内容が不十分であると、不採択となる可能性が高まると考えて良いでしょう。
たとえば、実現可能性の低い計画や課題への対応が曖昧な内容では、事業が成功しないと判断されかねません。
また、必要な記載事項が抜けている場合も不採択の原因となりうるため注意すべきです。
基本的には、専門家の支援を受けて作成されるため、実現不可能な内容になることは少ないはずですが、内容面で不採択となる可能性は十分にあります。
まとめ
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は50〜60%程度であり、数値だけを見ると高く感じられるかもしれません。
しかしこれは、多くが専門家の支援を受けた上での申請結果であり、十分に準備された上での数字です。
そのため、採択される可能性を高めるには、制度に精通した専門家の支援を受けることが求められます。
もし、依頼先の選定に困っているならば、F&M Clubの活用がおすすめです。
F&M Clubは中小企業のバックオフィス業務をサポートし、助成金の活用サポート範囲に含まれています。
助成金の情報提供など、幅広い支援が可能であるため、ぜひ、F&M Clubの活用をご検討ください。