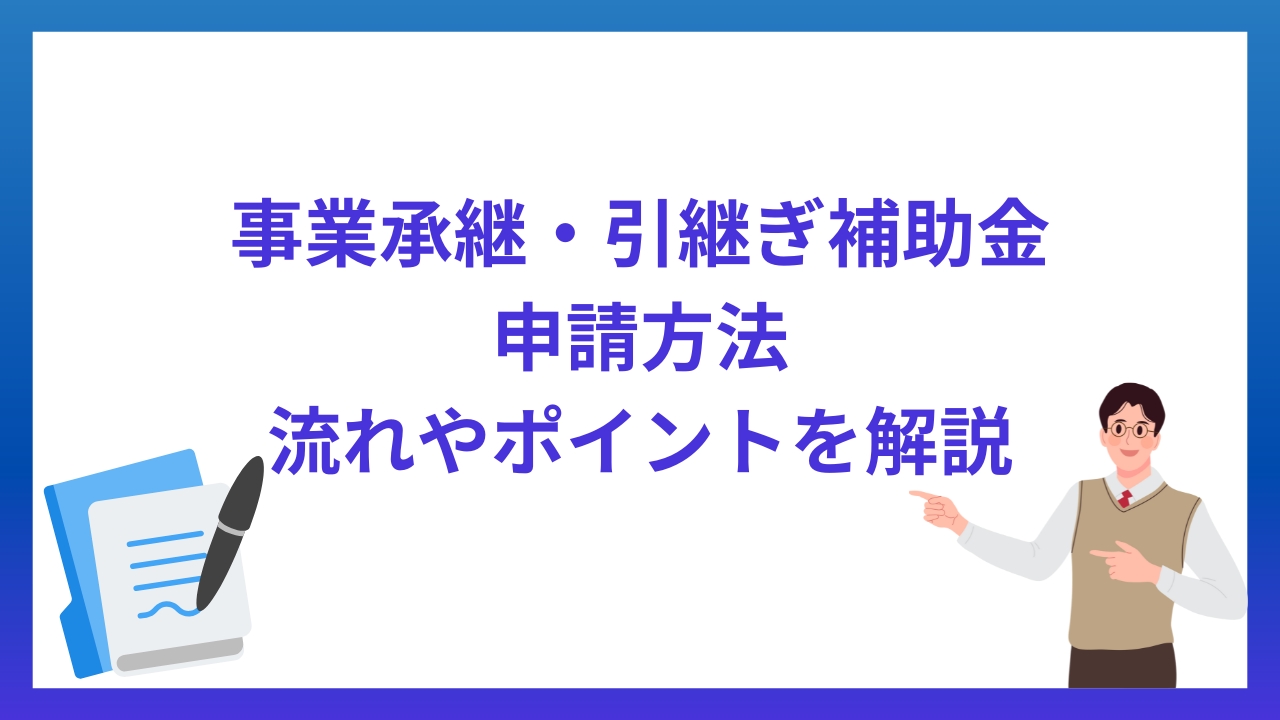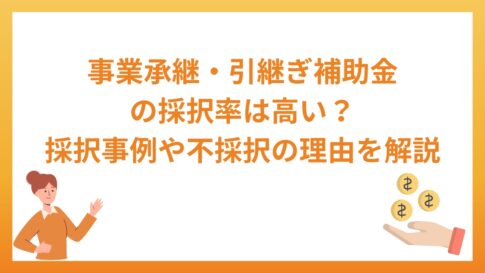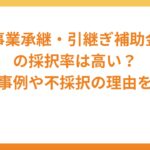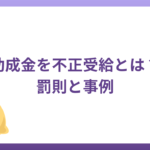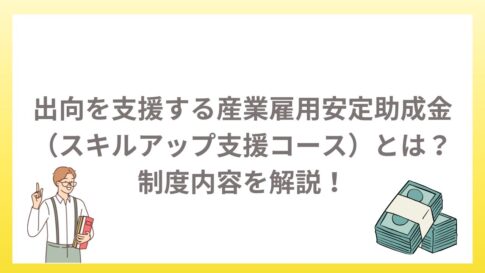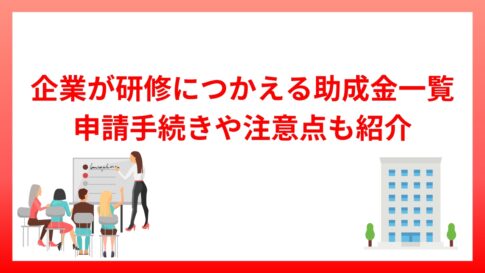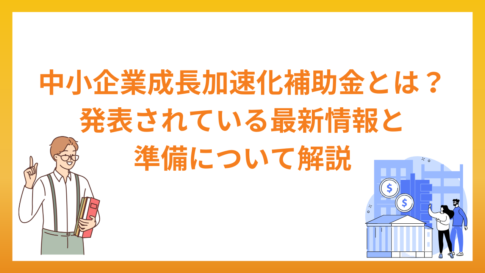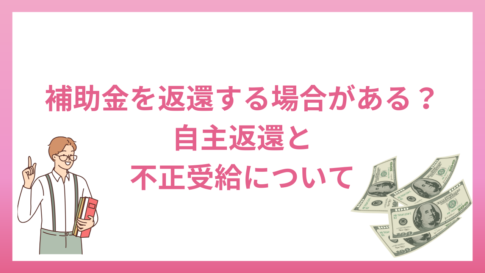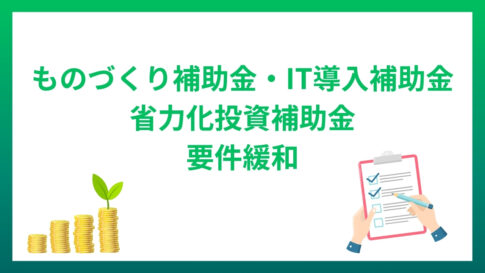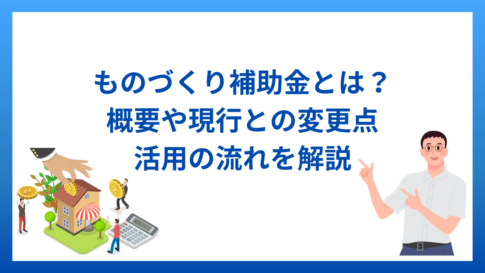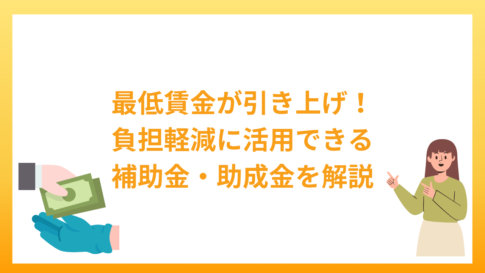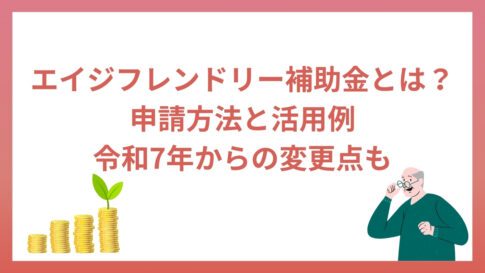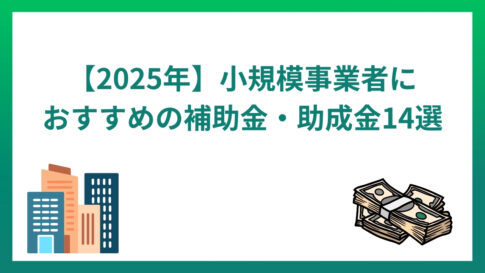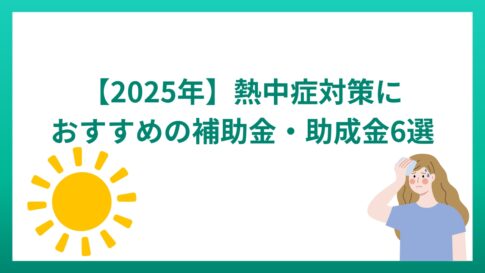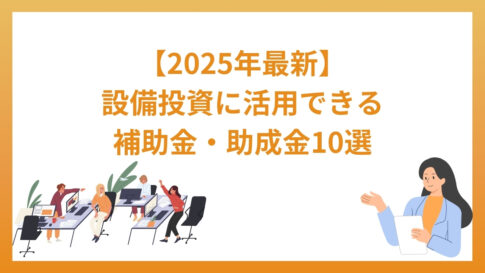事業承継・引継ぎ補助金は、既存の事業を承継・引継ぎする際に発生する費用を補助する制度であり、事業承継に向けた専門家の支援を受ける費用も対象となります。
事業承継・引継ぎ補助金に興味はあるけれど、申請方法や流れのイメージが湧かないという方も多いでしょう。
事業承継・引継ぎ補助金は補助金の概要から申請方法、採択に向けたポイントを解説します。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度は?
目次
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金とはどのような補助金であるか、概要や設けられている種類(枠)について解説します。
補助金の概要
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業や個人事業主が事業承継・事業再編・事業統合を契機に取り組む新たな挑戦などを支援する補助金です。
高額な費用が発生しがちなこれらの取り組みに対して、その経費の一部を補助することで、事業承継や事業再編を促進することを目的としています。
また、事業承継に向けた専門家の活用や、廃業する予定の事業を再構築する取り組みなども補助の対象です。
補助金の種類
事業承継・引継ぎ補助金には、主に以下の3つの申請枠が用意されています。
- 経営革新枠
- 専門家活用枠
- 廃業・再チャレンジ枠
基本的には、1回の公募でこれら3つの枠すべてが募集されます。
ただし、第10次公募では、専門家活用枠と廃業・再チャレンジ枠のみが対象とされていました。
今後も予算の都合や新たな補助金制度への移行に伴い、募集される枠が変更されるかもしれません。
常に、最新の公募要領に目を通し、どの枠が公募される予定であるか、確認することが大切です。
【参考】事業承継・引継ぎ補助金|事業承継・M&A補助金事務局
事業承継・引継ぎ補助金の申請方法と交付までの流れ
事業承継・引継ぎ補助金の申請方法と、交付までの流れを解説します。
gBizIDプライムアカウントなど事前準備
本補助金は「jGrants」と呼ばれるプラットフォームから申請します。
このサービスを利用するためには、事前準備として「gBizIDプライムアカウント」を発行しておかなければなりません。
本アカウントがなければ手続きができず、補助金に申請する機会を失ってしまいます。
公募期間は短く設定されているため、余裕を持ってアカウントの発行手続きを進めましょう。
時期にもよりますが、申請してから発行までに約2週間は、みておくと良いでしょう。
なお、別の補助金でgBizIDプライムアカウントをすでに発行している場合は、そちらのアカウントを用いて申請が可能です。
公募要領の確認
公募要領の詳細が発表されたら、内容を必ず確認しましょう。
申請を検討していても、最終的な公募要領で申請対象外の要件に該当してしまう可能性もあります。
最新情報に目を通し、申請できる事業者であるかの最終確認が重要です。
申請枠の決定
公募要領を確認し、申請資格があることを確認できたら、どの申請枠で申請するかを決定しなければなりません。
事業承継・引継ぎ補助金には複数の申請枠があり、補助上限額や補助率などの条件が異なります。
補助金を最大限活用するためには、自社にとって最も適した枠を選ぶことが重要です。
選択を誤ると不採択になったり、本来受け取れる金額より少なくなったりする可能性があります。
認定経営革新等支援機関への相談
事業承継・引継ぎ補助金のうち経営革新枠へ申請する場合は、「認定経営革新等支援機関」への相談が必須です。
申請にあたっては、事前に相談し、内容の確認や必要書類の準備などの支援を受けることが求められています。
たとえば、商工会議所や各金融機関などがこれに該当するため、相談しやすい機関を選択すればよいでしょう。
これまでに付き合いのある税理士や会計士などが該当する場合は、そちらに相談する方法もおすすめです。
なお、近くにどのような相談先があるかわからない場合は「認定経営革新等支援機関検索システム」を参照してください。
都道府県や支援機関の種別など複数の条件で検索できるため、どのような支援機関があるのかを一目で確認できます。
jGrantsより補助金の申請
公募が開始されると、jGrantsから申請が可能です。
必要な書類を電子ファイルで準備し、Webサイトの専用申請フォームから手続きをおこないましょう。
どのような書類が必要かは、申請枠ごとに公募要領へ記載されています。
書類の不足があると審査の対象にすらならないため、抜け漏れのない準備が必須です。
また、公募要領が修正され、必要な書類が変更されることもあるため、最新情報を常に確認することを心がけてください。
事務局による審査
申請後は、事務局によって審査が進められます。
審査の詳細は公開されていないため、審査結果が通知されるまで待機しなければなりません。
公募要領には、いつ頃結果が発表されるかの目安が記載されているため、それを参考に待ちましょう。
目安の期間を過ぎても結果の連絡が届かない場合は、事務局に問い合わせることをおすすめします。
審査結果の通知
事務局による審査が完了すると、jGrantsの画面上で結果が通知されます。
結果が更新されるとメールなどでも通知が届くため、必ずWebサイトへログインして確認しましょう。
通知のタイミングには目安期間が設定されており、公募要領などに記載されているため、そちらも参考にしてください。
無事に採択された場合には、その旨を伝える文章も提供されます。
内容をよく確認し、今後のスケジュールに備えましょう。
補助対象事業の実施
無事に審査を通過したら、提出した事業計画書に沿って、取り組みを進めていきましょう。
提出内容と異なる事業を実施すると、補助金が受給できない可能性があります。
これを避けるためにも、取り組み前に計画内容を再確認し、計画通りに実施するよう心がけてください。
また、最終的な報告時には、支払額を示す領収書や請求書などの資料が必要です
証跡を適切に保管し、支払い内容を可視化できる状態にしておきましょう。
実施結果・実績の報告
事業を遂行するだけでなく、最終的には「報告書」を通じて成果を事務局へ報告する必要があります。
この報告書が受理されて初めて、補助金が支払われる仕組みです。
報告書の内容に不備があると、補助金が減額されたり、不支給になったりする原因となりかねません。
ミスがないよう、十分に注意して作成してください。
補助金の交付
報告書の提出後には、事務局による最終確認が実施されます。
これは「計画書に沿って事業が遂行されたか」「経費が適切に支出されたか」などの確認です。
審査の結果、適切に事業が遂行されたと判断されれば、最終的に受給できる補助金額が算出されます。
最終的に補助金額が通知されるため、提示された金額に合意することで補助金の受給が確定します。
事業承継・引継ぎ補助金の申請を成功させるポイント
事業承継・引継ぎ補助金の申請を成功させ、採択されるためのポイントについて解説します。
専門家の支援を受ける
事業承継・引継ぎ補助金の申請には専門的な知識が求められます。
そのため、補助金申請の支援に慣れた専門家のサポートを受けることがポイントです。
ここでの専門家とは、「専門家活用枠」で登場する支援対象の専門家ではなく、補助金申請を支援する事業者などを指します。
申請には、提出書類の作成や情報収集、計画の精査など、多くの準備が必要です。
自力で対応すると大きな負担がかかるため、支援を受けながら申請することが望ましいでしょう。
加点ポイントをできるだけ取り入れる
申請に際しては「加点ポイント」が存在し、これを事業計画に取り入れると、採択の可能性が高まります。
加点ポイントの活用は必須条件ではないものの、取り入れると審査で高評価を得やすいという仕組みです。
申請枠ごとに異なる加点ポイントが設定されていて、例えば「経営革新枠」では以下が存在します。
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
- 「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けている
- 交付申請時点で「健康経営優良法人」である
なお、これらすべてを取り入れる必要はなく、ひとつでも取り入れられていれば、審査で有利に働く可能性があります。
まとめ
事業承継・引継ぎ補助金の申請方法は、他の補助金と大きな違いはありません。
必要な情報をキャッチアップし、公募開始に備えて事前準備を進めておきましょう。
ただし、本補助金を申請する際には、事前に「認定経営革新等支援機関」への相談が必要です。
相談先を探すことや、計画の作成には時間がかかる可能性があるため、十分な余裕を持って準備を進めることが大切です。
なお、補助金の活用や申請方法に不安があるならば、F&M Clubの活用がおすすめです。
F&M Clubは中小企業のバックオフィス業務をサポートし、助成金の活用も幅広くサポートしています。
事業承継・引継ぎ補助金の情報提供など、幅広い支援が可能であるため、ぜひ、F&M Clubの活用をご検討ください。