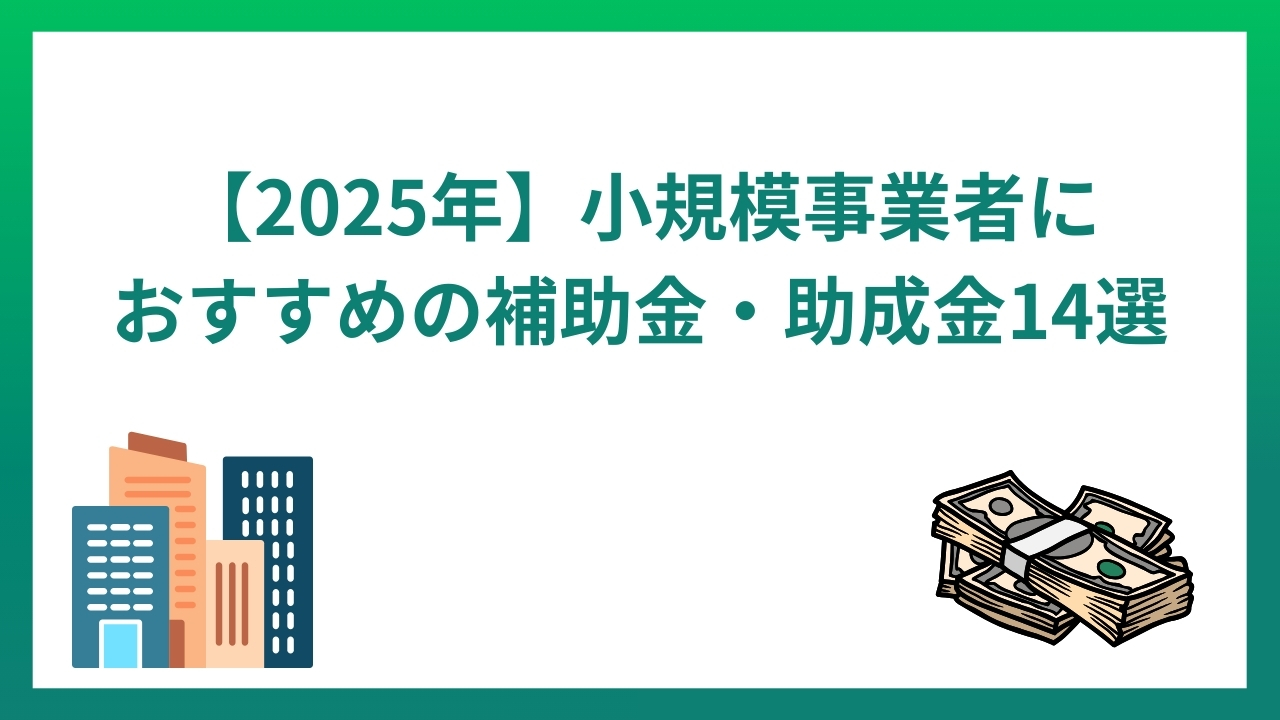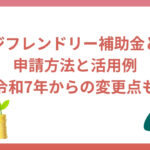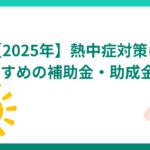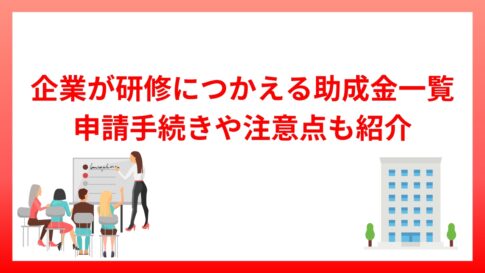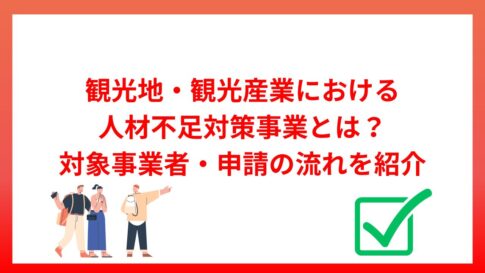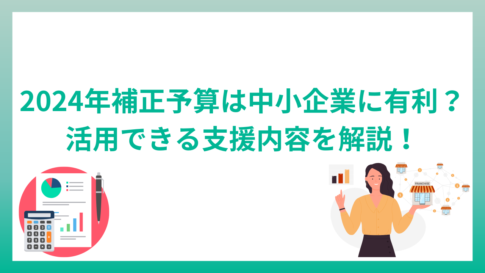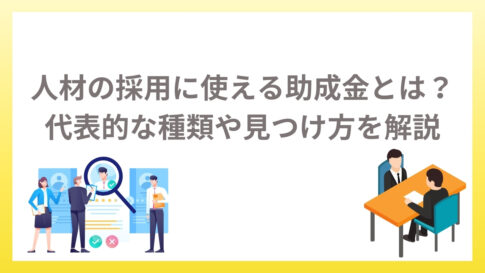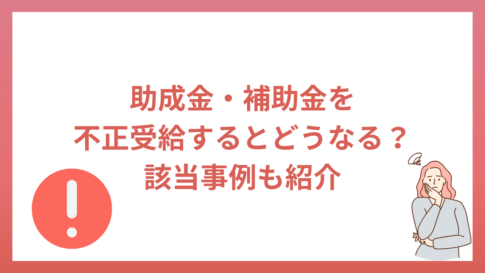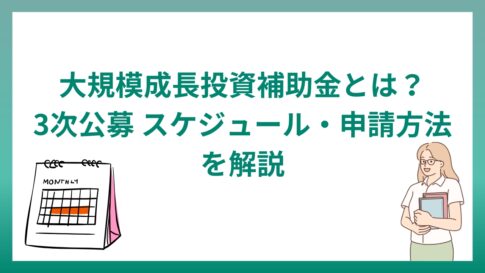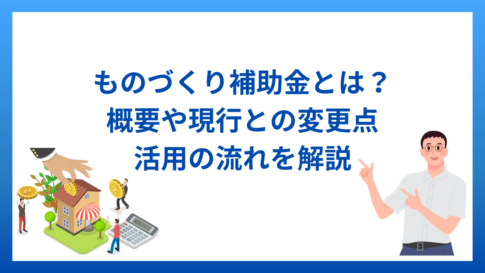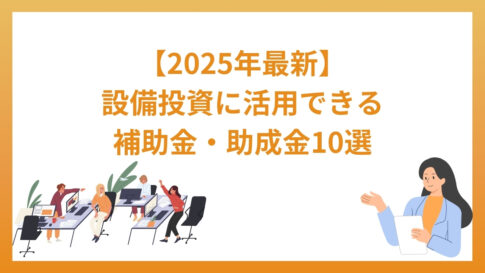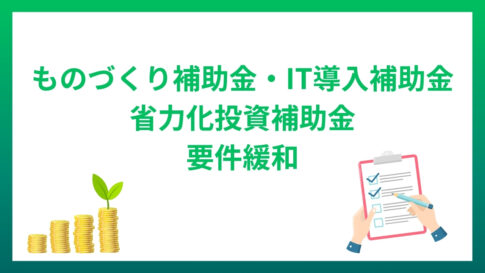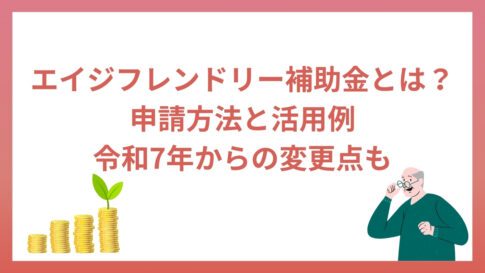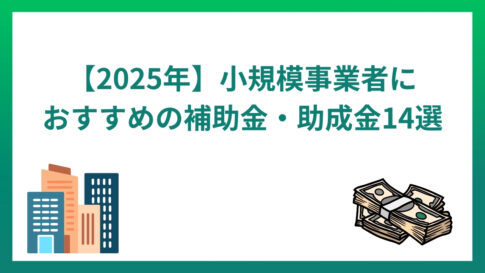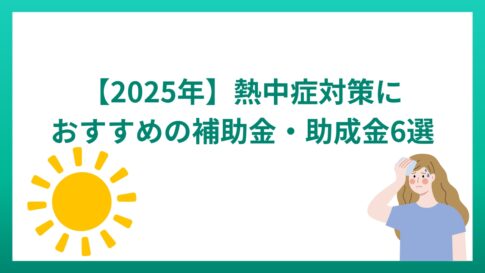事業の成長に向けて、「新しい設備を導入したい」「労働環境を良くしたい」などの思いを抱える小規模事業者も多いでしょう。しかし、日々の資金繰りや人手不足で上記の取り組みができずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。上記のようなケースで活用したいのが、返済不要で設備導入や労働環境の整備に必要な資金を調達できる補助金・助成金制度です。
本記事では、小規模事業者におすすめの補助金・助成金を16個ピックアップして紹介し、ほかの支援制度も含めて紹介します。本記事を読めば、小規模事業者が利用できる補助金・助成金のなかから自社にあったものをスムーズに選んで申請できます。補助金・助成金制度を活用し、早期に自社の経営を安定化させましょう。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度は?
目次
小規模事業者とは

小規模事業者とは、中小企業の中でも特に規模が小さい事業者を指す言葉です。中小企業法の第2条第5項によって明確に定義されており、常時使用する従業員の数で判断されるのが大きな特徴です。具体的には、以下の人数以下の事業者が小規模事業者に該当します。
- 製造業・建設業・運輸業やそのほかの業種(卸売業、サービス業、小売業は除く):20名以下
- 卸売業・小売業・サービス業:5名以下
上記の基準を満たしていれば、株式会社などの法人だけでなく個人事業主・フリーランスもすべて小規模事業者に含まれます。
中小企業・個人事業主との違い
中小企業は経営規模が規定内である中小規模の企業を指し、中小企業基本法では以下の基準を満たすと該当します。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
| 製造業、建設業、運輸業、そのほかの業種(卸売業、サービス業、小売業は除く) | 3億円以下 | 300名以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100名以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50名以下 |
例えば、製造業であれば「資本金3億円以下」または「従業員300名以下」のどちらかを満たせば中小企業です。一方で、個人事業主とは法人を設立せずに個人で事業を営む人を指し、フリーランスや店舗を経営する店主などが該当します。
中小企業でも「みなし大企業」に区分されるケースがある
みなし大企業とは企業規模自体は中小企業の定義に当てはまるものの、実質的に大企業の支配下にあると判断される企業を指す言葉です。みなし大企業の区分は、実質的に大企業の傘下にある中小企業を補助金などの支援対象から除くために設けられたルールです。
補助金制度の趣旨は、自力での資金調達が比較的困難な独立した中小企業・小規模事業者を優先的に支援する点にあります。そのため、親会社の大企業から十分な支援を受けられるような資金力がある企業は対象外です。
みなし大企業の具体的な定義は法律で一律に定められているわけではなく、利用したい補助金や支援制度の公募要領ごとに個別に規定されています。例えば、事業再構築補助金では、みなし大企業に該当するケースとして以下の項目を掲げています。
- 単一の大企業が株式の2分の1以上を所有している
- 複数の大企業が株式の3分の2以上を所有している
- 大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を兼務している
- みなし大企業が株式のすべてを所有している
- みなし大企業の役職員が役員のすべてを兼務している
- 課税所得の年平均額が15億円を超える
上位の条件にひとつでも当てはまると、自社の資本金や従業員数が中小企業の範囲内であっても申請資格を失います。特に、大企業からの出資を受けている場合や役員の派遣を受け入れている場合は注意が必要です。
大企業の具体的な定義は定められていない
日本の法律では、大企業そのものを明確に定義した条文は存在しません。そのため、一般的には中小企業法で定義される中小企業の規模を超える企業が大企業として認識されています。
例えば、製造業の場合、中小企業の定義は資本金3億円以下または常時使用する従業員数300名以下です。したがって、上記の裏返しである資本金3億円を超え、かつ常時使用する従業員数が300名を超える企業が大企業と解釈できます。
小規模事業者が利用できるおすすめの補助金6選
ここでは、小規模事業者が利用できるおすすめの補助金を6つピックアップして紹介します。
上記のなかから、申請条件に合致する補助金を選んで申請しましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するための補助金です。小規模事業者持続化補助金における最大の魅力は、補助金を使える用途の広さにあります。チラシやウェブサイトの作成などの広報活動から店舗の改装、新たな設備投資まで事業の持続的な発展につながる幅広い経費が対象です。
なお、近年ではインボイス対応や賃上げに取り組む事業者に対して補助上限額が引き上げられる特別枠も設けられています。多くの事業者が申請サポートを提供しており、初めて補助金を申請する方にとっても比較的取り組みやすい制度です。
| 補助率 | 3分の2〜4分の3 |
| 補助上限額 | 50万円 |
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する経費の一部を補助して業務効率化や生産性向上をサポートする制度です。IT導入補助金の特徴は、あらかじめ事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するITツールのみが補助対象となる点です。会計ソフト・受発注システム・決済ソフトなどの業務効率化ツールから、顧客管理・マーケティングオートメーションツールまで多種多様なものが登録されています。
IT導入補助金ではIT導入支援事業者と共同で事業計画を作成し、申請手続きを進めていく形式を取ります。申請者自身がITに詳しくなくても、専門家のサポートを受けながら自社に最適なツールを選定し、導入を進められる点が大きなメリットです。
| 補助率 | 2分の1~5分の4 |
| 補助上限額 | 3,000万円 |
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者の革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を目的とした設備投資を支援する補助金です。補助額が最大8,000万円と比較的大きく、本格的な設備投資を検討している事業者にとって非常に魅力的な制度です。
ものづくりの名称から製造業向けのイメージが強いですが、実際には商業・サービス業など幅広い業種が対象となります。例えば、以下のような取り組みも、ものづくり補助金の補助対象に含まれます。
- 飲食店が最新の調理機器を導入して新メニュー開発をおこなう
- サービス業で新たなサービス提供のためのシステムを構築する
| 補助率 | 2分の1〜3分の2 |
| 補助上限額 | 8,000万円 |
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aをきっかけとした新たな挑戦にかかる経費を幅広く支援する制度です。事業承継・M&A補助金の大きな特徴は事業承継やM&Aのプロセスだけでなく、後の経営革新までを一貫してサポートしてくれる点にあります。具体的には、事業承継・M&Aの実施前後に関わる以下のような幅広い費用が補助対象となります。
- M&Aの際に相手企業の価値を調査するデューデリジェンスにかかる専門家費用
- 事業を引き継いだ後継者が新たな顧客層を開拓するためにおこなう店舗改装費用
- 新商品開発のための設備投資
事業を引き継ぐ際の金銭的なハードルを下げるだけでなく、承継後の事業をさらに成長させるための投資を後押ししてくれる制度です。
| 補助率 | 2分の1~3分の2 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、IoTやロボットなど人手不足解消に効果的な省力化製品の導入支援を目的とした制度です。中小企業省力化投資補助金の特徴は、事業者が製品を選びやすいカタログ形式を採用している点です。
事務局が性能・価格を審査して認定した製品がカタログに掲載され、事業者は自社の課題解決に最適なものを選んで導入できます。そのため、製品選びの手間が省け、一定の品質が担保された製品を導入できる点がカタログ形式の大きなメリットです。対象となる製品は飲食店の配膳や清掃ロボット、宿泊業の自動チェックイン機、小売業の自動釣銭機など多岐にわたります。
| 補助率 | 3分の1〜3分の2 |
| 補助上限額 | 1億円 |
省エネルギー投資促進支援事業費補助金
省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、事業者が高効率な省エネ設備へ更新する際の費用を補助する制度です。省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、エネルギーコストの削減と国の目標であるカーボンニュートラルの実現を目的としています。
省エネルギー投資促進支援事業費補助金はいくつかの事業類型に分かれていますが、小規模事業者が最も利用しやすいコースは設備単位型です。事務局が定めた高い省エネ性能をもつ設備を導入する場合に利用できるもので、具体的には以下が補助対象となります。
- 高効率空調
- LED照明
- 業務用給湯器
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
古い設備を最新のものに入れ替えれば、故障リスクが低減してメンテナンスコストの削減にもつながります。
| 補助率 | 3分の1〜4分の3 |
| 補助上限額 | 15億円 |
小規模事業者が利用できるおすすめの助成金8選
小規模事業者が利用できるおすすめの助成金として、以下の8個を紹介します。
自社の解決したい労働環境上の課題に合わせて、上記の助成金を使い分けましょう。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、事業活動が縮小した事業主が従業員を解雇せずに一時的な休業や教育訓練、出向によって雇用を維持した場合に利用できる制度です。雇用調整助成金を利用すれば、従業員に支払う休業手当の一部を国が助成してくれます。
「売上が急に減少した」「取引先からの発注が途絶えた」といった際に、助成金を活用して従業員の生活を守りながら事業の再建を目指せます。雇用調整助成金の申請には、休業計画届の提出や実際に休業手当を支払った実績などが必要です。
| 助成率 | 2分の1〜3分の2 |
| 助成額(上限) | 1名1日あたり8,635円 |
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者のキャリアアップを促進するために正社員への転換や処遇の改善に取り組んだ事業主に対して支給される助成金です。キャリアアップ助成金には複数のコースがありますが、最も利用しやすいのが正社員化コースです。
正社員化コースは有期雇用労働者などを正規雇用に転換した場合に助成されるもので、従業員のモチベーション向上と定着率アップに直結します。ほかにも、非正規雇用労働者の賃金規定を改定して昇給させる賃金規定等改定コースなど企業の状況に合わせたさまざまな取り組みが支援対象です。
| 助成額(一例) | 【正社員化コース】 重点支援対象者:1名あたり30〜80万円上記以外の一般対象者:1名あたり15〜40万円 |
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、育児や介護と両立して従業員が働き続けられるよう支援制度の導入などに取り組む事業主をサポートする助成金です。両立支援等助成金は、以下のように助成対象となる取り組みに応じて複数のコースに分かれています。
| 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性の労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた場合に支給される |
| 介護離職防止支援コース | 介護支援プランを策定し、介護休業の取得や職場復帰をしやすい環境を整備した場合に支給される |
| 育児休業等支援コース | 育休復帰支援プランを策定し、労働者の円滑な育児休業の取得と職場復帰を支援した場合に支給される |
| 不妊治療両立支援コース | 不妊治療と仕事の両立ができるよう休暇制度や柔軟な勤務制度を導入し、労働者が利用しやすい環境を整備した場合に支給される |
| 育休中等業務代替支援コース | 育児休業取得者や短時間勤務者の業務を、周囲の労働者が代替する際の業務体制の整備をおこなった場合に支給される |
小規模事業者においては、一人の従業員が休むだけでも業務への影響は小さくありません。しかし、両立支援等助成金を活用して代替要員の確保や業務分担の見直しをおこなえば、安心して働ける業務環境を築けます。
| 助成額(一例) | 【出生時両立支援コース】 1人目の育休取得:20万円2人目以降の育休取得:1名あたり10万円 |
業務改善助成金
業務改善助成金は事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などをおこなった場合に助成を受けられる制度です。業務改善助成金の特徴は賃上げと生産性向上を同時に支援してくれる点で、具体的には以下のような取り組みがおこなえます。
- POSレジシステムを導入して会計業務の時間を短縮し、生まれた利益を原資としてパートタイムの時給を50円アップさせる
対象となる設備投資も幅広く業務効率化につながるものであれば、専用のソフトウェアや厨房機器、運搬用の小型トラックの導入なども助成対象です。賃上げの負担を軽減しながら企業の収益力を高める投資ができるため、従業員の満足度向上と企業の競争力強化を同時に目指せます。
| 助成率 | 4分の3~5分の4 |
| 助成額 | 30万円~600万円 |
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は従業員にとって魅力的な職場環境を整備し、人材の定着・確保を図る事業主を支援するための制度です。人材確保等支援助成金では、従業員の離職率低下を目的とした非常に多岐にわたる申請コースが用意されています。
| コース名 | 目的・概要 |
| 雇用管理制度助成コース | 魅力ある雇用管理制度の導入を通じて、人材の定着・確保を図る |
| 人事評価改善等助成コース | 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備・実施し、生産性の向上、賃金アップ、離職率の低下を図る |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人労働者が働きやすい環境を整備し、職場定着を図る |
| テレワークコース | 良質なテレワークを制度として導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理の改善を図る |
| 建設キャリアアップシステム等普及促進コース | 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用を通じて、建設技能者の処遇改善に取り組む |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース | 若年者や女性労働者の入職・定着を図るため、魅力的な職場づくりに取り組む |
| 作業員宿舎等設置助成コース | 被災三県(岩手・宮城・福島)における作業員宿舎の設置や、女性専用作業員施設の設置・賃借を行う |
例えば、雇用管理制度助成コースでは従業員のスキルアップのための研修制度などを導入し、離職率が目標値を下回った場合に助成金が支給されます。また、人事評価改善等助成コースでは生産性向上につながる人事評価制度を整備し、実際に賃金アップなどを実現した場合に助成が受けられます。
| 助成額(一例) | 【雇用管理制度助成コース】諸手当、賃金規定、人事評価制度の導入:1制度あたり40万円健康づくり、職場活性化制度の導入:1制度あたり20万円1事業主あたり80万円が上限 |
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳を超えても従業員が安心して働き続けられるような雇用環境を整備した事業主に対して支給される助成金です。65歳超雇用推進助成金には、取り組み内容に応じて、以下のように3つのコースがあります。
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引き上げ、定年制度の廃止など高年齢者の雇用機会を確保する措置をおこなった場合に支給される |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者が意欲や能力に応じて活躍できるよう、能力開発・賃金体系といった雇用管理制度の整備をおこなった場合にかかった経費の一部が支給される |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた場合に支給される |
長年培ってきた技術やノウハウをもつベテラン従業員に長く活躍してもらうことは、企業の技術継承や人材不足の解消に直結します。
| 助成額(一例) | 【65歳超継続雇用促進コース】65歳への定年引き上げ:20万円70歳以上への定年引き上げ:30万円 |
産業雇用安定助成金
産業雇用安定助成金は、在籍型出向を利用して従業員の雇用を維持する出向元の事業主と従業員を受け入れる出向先の事業主の双方を支援する制度です。在籍型出向とは、出向元の企業との雇用契約を維持したまま、人手を必要とする出向先で勤務する働き方です。
産業雇用安定助成金を活用すれば、出向元の企業は人件費の負担を軽減しつつ従業員の雇用を守れます。一方、出向先の企業は採用コストをかけずに必要なスキルをもつ人材を一時的に確保できる点がメリットです。
| 助成率・助成額(一例) | 【雇用維持支援コース】出向運営経費:2分の1〜5分の4出向初期費用:1名あたり10万円出向復帰後訓練費用:訓練経費の実費(上限30万円) |
テレワークトータルサポート助成金
東京都が運営するテレワークトータルサポート助成金は、都内に本社または事業所を置く中小企業を対象にテレワークの導入・拡大を支援する制度です。テレワークトータルサポート助成金は、テレワーク環境の整備に必要な幅広い経費を対象としているのが魅力です。具体的には、従業員に貸与するノートPCやタブレットなどの購入費用から、Web会議システムやクラウド型勤怠管理ソフトの利用料まで多岐にわたります。
テレワークトータルサポート助成金の申請にあたっては、東京都が実施するテレワーク相談窓口の利用が要件となっています。相談窓口でテレワークの導入に関するアドバイスを受けながら、計画的に環境整備を進められる点が大きなメリットです。
| 助成率 | 3分の2 |
| 助成額 | 150〜250万円 |
小規模事業者が補助金・助成金を申請する流れ・ステップ
補助金・助成金を申請する流れは制度によって大きく異なりますが、一般的には以下の流れで進めます。
| ステップ | 主な内容 | ポイント |
| Step1 | 情報収集・制度の選定 | 自社の課題を明確にし、解決につながる補助金・助成金制度を探す |
| Step2 | 公募要領の確認 | 対象事業者・対象経費・スケジュールなど申請に関わる部分を確認する |
| Step3 | 事業計画の策定・申請準備 | 事業計画書や就業規則など、補助金・助成金ごとに必要な資料を準備する |
| Step4 | 申請手続き | 電子申請システムなど、指定された方法で期間内に申請を完了させる |
| Step5 | 審査・交付決定 | 事務局による審査がおこなわれ、採択されると交付決定通知書などが届く |
| Step6 | 事業の実施・経費の支払い | 交付決定日以降に、計画に沿って契約・発注・支払いをおこなう |
| Step7 | 実績報告 | 事業完了後、かかった経費の証拠書類を添えて報告する |
| Step8 | 確定検査・金額の確定 | 提出された報告書を基に事務局が検査をおこない、最終的な支給額が確定する |
| Step9 | 請求・入金 | 確定した金額を事務局に請求し、指定した口座へ入金される |
小規模事業者が補助金・助成金を利用するメリット
小規模事業者が補助金・助成金を利用するメリットとして、以下の4点があげられます。
補助金・助成金を利用するメリットは多岐にわたるため、申請条件が合う制度は積極的に利用しましょう。
返済不要の資金が手に入る
補助金・助成金を利用するメリットは、返済不要な資金が手に入る点です。金融機関からの借入は返済が必要であり、自己資金に余裕がない小規模事業者にとっては将来の返済負担が大きくなります。
しかし、補助金・助成金では返済負担がなく、利益を圧迫せずに経営を安定させやすい点がメリットです。そのため、自己資金だけでは躊躇してしまうようなリスクを伴う新たな設備投資や新商品・サービスの開発、販路拡大に取り組めます。
事業の価値が向上する
補助金・助成金で採択されれば、自社の事業計画が国・公的機関からお墨付きを得た証となり、企業の社会的信用度を大きく向上させます。なぜなら、審査で事業の新規性や市場での優位性・収益性などを専門家によって客観的かつ厳格に評価されるためです。
また、補助金・助成金を申請するプロセス自体にも大きな価値があります。事業計画書を作成する過程で自社の強みや弱み、競合の動向、市場環境などを深く分析して将来のビジョンを具体的に言語化しなければなりません。経営者自身が事業の本質を見つめ直し、今後の経営戦略を練り上げる絶好の機会となります。
そして、一度採択の実績を得られれば、金融機関の融資審査においても有利に働くケースがあります。国・公的機関が認めた事業計画であるため、返済能力を示す材料となり、追加の資金調達がスムーズに進む可能性が高いです。また、取引先・顧客に対しても国が成長性を認めた企業としてアピールでき、商談やブランディングの面で大きな信頼を得られます。
労働環境の整備や生産性の向上を図れる
補助金・助成金は、労働環境の整備や生産性の向上を図れる点も大きなメリットです。特に、厚生労働省が管轄する助成金を活用すれば、従業員が働きやすい環境を整備して人材の定着と満足度の向上を図れます。例えば、助成金を活用して労働環境に関する以下のような取り組みが可能です。
- キャリアアップ助成金で非正規社員の正社員化を進める
- 両立支援等助成金で育児・介護と仕事を両立できる制度を整える
また、IT導入補助金やものづくり補助金などを活用すれば、経済的負担を抑えながら事業の生産性を飛躍的に向上させられます。今まで人手に頼っていた単純作業・事務作業を、最新のITツールや機械設備で自動化・効率化が可能です。従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになり、残業時間の削減や収益性の改善につながります。
事業主の負担を抑えて賃上げを実施できる
助成金を活用すれば、事業主の実質的な負担を抑えながら従業員の賃金引き上げを実現できます。たとえば、業務改善助成金は事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上に資する設備投資をセットでおこなう事業者を支援する仕組みです。業務改善助成金を利用すれば、賃上げを実現した上で設備投資にかかった費用の一部について助成が受けられます。
助成金を活用すると経営者は賃上げの決断を下しやすくなり、同時に生産性向上によって企業の収益力も強化できます。一方、従業員は収入が増えると生活が安定して仕事へのモチベーションも高まるため、双方にメリットが大きいです。
補助金・助成金以外に小規模事業者が利用できる支援制度・施設
補助金・助成金以外に小規模事業者が利用できる支援制度・施設として、以下の5つを紹介します。
自社の課題に応じて、上記の支援制度・施設を使い分けましょう。
中小企業支援センター
中小企業支援センターは、各都道府県に設置されている中小企業・小規模事業者のための経営に関する総合相談窓口です。売上拡大・資金繰り・人材育成・IT活用・事業承継など、経営に関するあらゆる悩みを原則無料で相談できる公的機関です。
中小企業支援センターの窓口には、中小企業診断士などの資格をもつコーディネーターが常駐しています。コーディネーターは事業者一人ひとりの話に耳を傾け、課題の整理から解決策の提案までを親身におこなってくれます。相談内容に応じて、税理士・弁護士など外部の専門家を無料で派遣してくれる専門家派遣制度を設けている場合も多く、高度な課題にも対応が可能です。
経営改善普及事業
経営改善普及事業は、全国の商工会議所・商工会が実施している経営支援事業です。経営指導員が常駐しており、金融・税務・経理・労務など日々の事業運営で生じるさまざまな問題について相談に乗ってくれます。また、マル経融資の推薦や地域の金融機関への紹介など金融相談をおこなってくれる点も特徴です。
なお、小規模事業者持続化補助金などの補助金では、申請にあたって商工会議所・商工会で事業計画の確認書を発行してもらうことが要件となっています。経営指導員は計画策定の段階から伴走支援してくれるため、補助金の活用を考えている事業者にも有用です。
マル経融資
マル経融資は、商工会議所・商工会の経営指導を受けている小規模事業者が無担保・無保証人で利用できる日本政策金融公庫の融資制度です。マル経融資のメリットは無担保・無保証人で融資を受けられる点で、不動産などの担保や保証人を用意する必要がなく経営者個人の保証も原則不要です。国の政策として実施されているため、金利も非常に低く設定されており、長期で安定した返済計画を立てやすい点も大きな魅力です。
資金繰りに悩む小規模事業者にとって、まずはじめに検討したい融資制度のひとつです。
なお、マル経融資を利用するためには原則として6カ月以上、商工会議所・商工会の経営指導を受けていることが前提となります。
小規模企業者等設備貸与事業
小規模企業者等設備貸与事業は機械設備を都道府県などの中小企業支援機関が代わりに購入し、小規模事業者へ長期・低利で提供してくれる制度です。小規模企業者等設備貸与事業のメリットは、高額な設備を導入する際の初期投資を大幅に抑えられる点にあります。
購入代金は公的機関が立て替えてくれるため、手元の資金を運転資金に回せば、資金繰りに余裕が生まれます。利率が低く設定されており、支払期間も長期に設定できるため、月々の負担を軽減しながら計画的な返済が可能です。
対象となる設備は製造業の工作機械やIT関連のサーバー、飲食店の厨房機器、建設業の重機など幅広く、さまざまな業種で活用できます。支払いが完了すれば自社の所有物となる「割賦」と期間満了後に返却や再リースを選択できる「リース」があり、自社の経営計画に合わせて選べます。
小規模企業共済
小規模企業共済は、退職金がない個人事業主や会社役員のための退職金制度です。小規模企業共済の魅力は掛金が全額所得控除の対象になり、節税効果を期待できる点です。毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲で自由に設定できますが、全額が課税対象となる所得から差し引かれます。
さらに、積み立てた共済金を受け取る際も一括であれば退職所得、分割であれば公的年金などの雑所得として扱われ、税制上の優遇が受けられます。また、納付した掛金の範囲内で事業資金などを低利で借り入れできる貸付制度もあり、資金不足時の保険としても活用が可能です。
小規模事業者が補助金・助成金を活用する際は「F&M Club」を利用しよう

小規模事業者が補助金・助成金を活用する際は、累計48,000社の導入実績がある「F&M Club」の利用がおすすめです。月額制で利用できる「F&M Club」は中小企業のバックオフィス業務を幅広くサポートしており、補助金・助成金に関する以下のサービスも提供しています。
- 簡単なアンケートに答えて貴社にあった補助金・助成金制度のレポートを配信
- アンケート結果から条件に該当する助成金を診断
- 補助金・助成金における申請書の策定支援から申請代行までサポート
専門スタッフが最新の補助金・助成金情報をタイムリーに提供してくれるため、情報収集の手間が大幅に削減されます。さらに、採択の鍵となる事業計画書の作成や煩雑な申請手続きについても専門家の知見を借りながら丁寧に進められる点も魅力です。本業に集中しながらも補助金・助成金をスムーズに受給したい小規模事業者は、ぜひ「F&M Club」の活用を検討してください。
小規模事業者が利用できる補助金・助成金に関するよくある質問
小規模事業者が利用できる補助金・助成金に関するよくある質問として、以下の4つをピックアップして紹介します。
補助金・助成金に関して疑問点がある場合は、上記質問への回答を参考にしてください。
補助金・助成金は誰でも申請できる?
補助金・助成金は誰でも申請できるわけではなく、各制度には対象となる事業者の要件が定められています。補助金・助成金は、税金・雇用保険料などを財源として特定の政策目的を達成するために実施されているためです。
具体的には、公募要領に記載されている対象事業者の項目に申請できる事業者の条件が記載されています。例えば、小規模事業者持続化補助金であれば、常時使用する従業員数が5名または20名以下の規定を満たさなければなりません。
個人事業主でも申請できる補助金・助成金はある?
個人事業主が申請できる補助金・助成金は数多くあります。たとえば、小規模事業者持続化補助金は個人事業主も対象事業者にしており、販路開拓のためのチラシ作成やウェブサイト構築などを支援してくれます。
ほかにも、IT導入補助金やものづくり補助金なども公募要領に記載されている要件を満たせば個人事業主も申請が可能です。また、従業員を雇用している個人事業主の場合は雇用の安定や人材育成を目的とした厚生労働省の各種助成金も申請対象となります。
補助金・助成金は申請してすぐに受け取れる?
補助金・助成金は申請してすぐには受け取れず、対象事業を実施した後に報告書を提出して受給する後払いが一般的です。そのため、申請して採択されたとしても実際の入金は計画した事業をすべて完了し、経費の支払いを終えた後となります。
そのため、交付決定から実際の入金までには数カ月、場合によっては1年近くかかるケースもあります。補助金・助成金をあてにして事業を始めたものの、立て替え払いの資金が足りずに計画が頓挫するケースも少なくありません。必ず、事業実行のためのつなぎ資金を事前に準備しておきましょう。
補助金と助成金にはどのような違いがある?
補助金と助成金はどちらも返済不要な資金ですが、主に以下の違いがあります。
| 比較項目 | 補助金 | 助成金 |
| 目的 | 新規事業や設備投資など、国の政策目標を達成するために事業者を支援する | 雇用の安定や人材育成など、法令で定められた要件を満たす活動を支援する |
| 主な所管省庁 | 経済産業省、地方自治体など | 厚生労働省 |
| 受給の難易度 | 予算と採択件数が決まっており、審査で優れていると判断されないと受給できない | 定められた要件をすべて満たせば、原則として受給できる |
| 審査のポイント | 事業計画の新規性・市場性・実現可能性など、内容の優劣が評価される | 申請要件を満たしているか、手続きが適正かなどが確認される |
| 公募・申請期間 | 公募期間が比較的短く、期間限定の場合が多い | 通年で受け付けている場合が多い |
補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄し、国の産業政策や地域の活性化を目的としています。公募期間内に申請のあった事業者のなかから、事業計画の優れたものが審査によって選ばれる形式です。
一方で、助成金は主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働環境の改善、人材育成などを目的としています。定められた要件をすべて満たせば、原則として受給できる点が補助金との大きな違いです。
まとめ
小規模事業者の経営は資金繰りや人材確保など課題の連続で、支援のために国・自治体は返済が不要な補助金・助成金制度を用意しています。IT化による生産性向上や従業員の待遇改善など自社の目的に合った補助金・助成金を見つけて活用すれば、経済的負担を抑えながら経営をスムーズに成長軌道へと乗せられます。
補助金・助成金の申請前には基本要件の確認が必要で、条件を満たしていないと申請を受け付けてもらえません。また、無担保・無保証のマル経融資や経営者の退職金となる小規模企業共済など、ほかの支援制度も数多く存在します。上記の公的支援に関する情報を積極的に収集し、専門家の力も借りながら事業の持続的な成長を実現しましょう。
「自社で使える補助金や助成金を知りたい」「補助金・助成金について、誰に相談すれば良いかわからない」という悩みを抱えている方には、累計48,000社以上の中小企業のバックオフィス業務を支援したF&M Clubがおすすめです。
F&M Clubは、補助金申請・採択件数で全国トップラスの実績をもつ、エフアンドエムが提供する経営者向けのサブスクサービスです。
豊富な補助金申請支援実績などから得た“本当に役立つ”経営ノウハウ、資金繰り改善、補助金や助成金申請のサポートなどが、月額30,000円(税抜)でお好きなだけご利用いただけます。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度は?