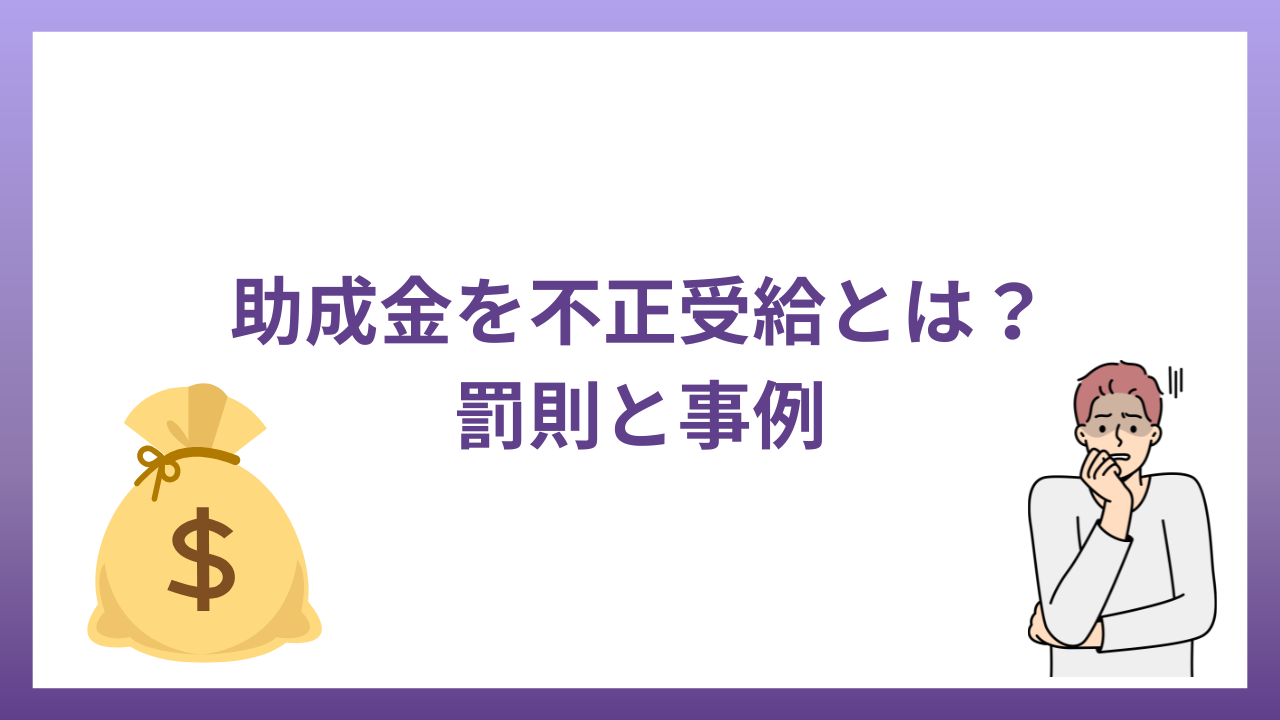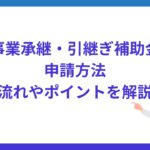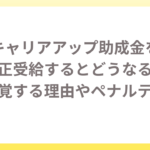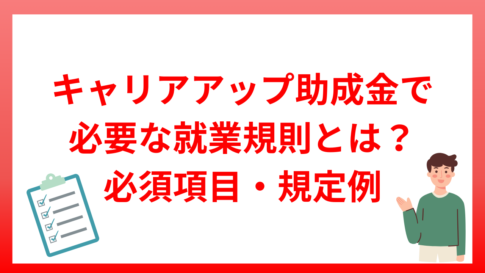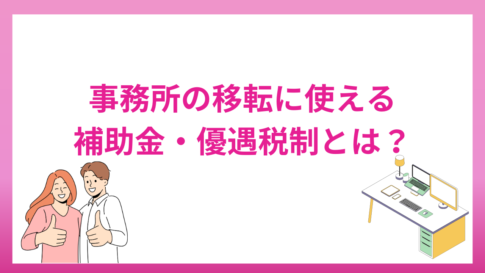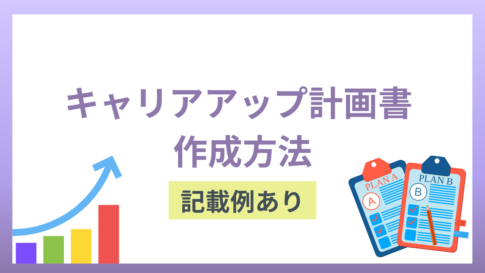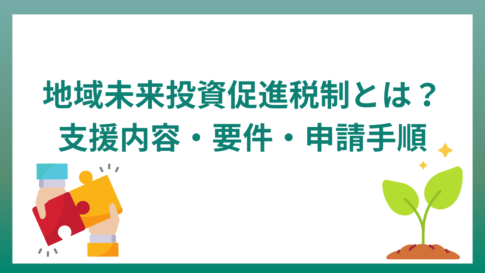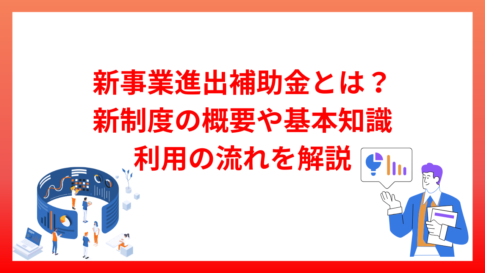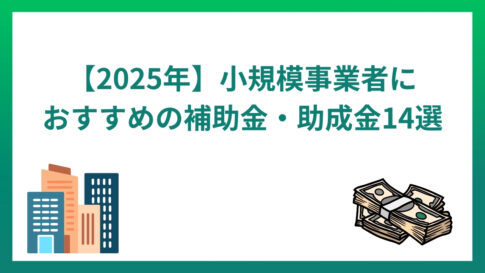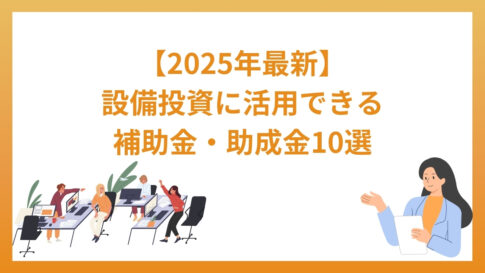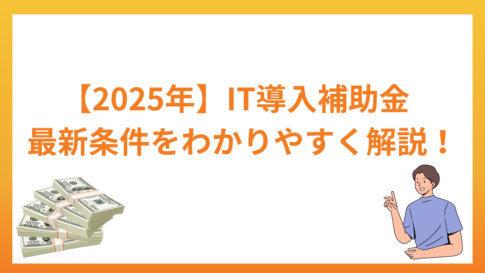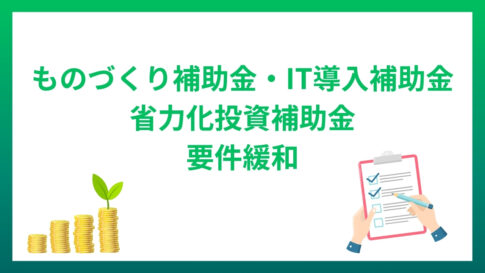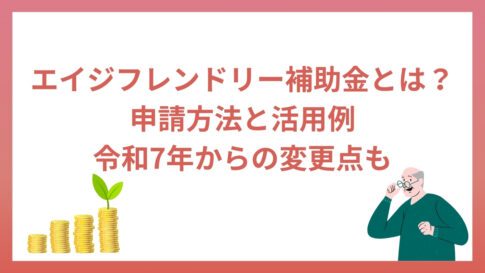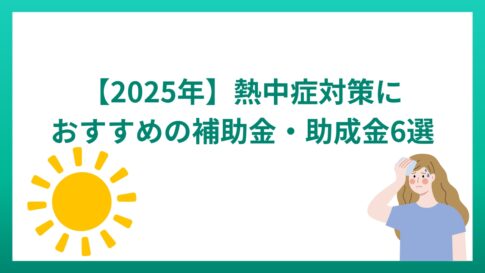助成金を不正受給すると、返還命令が出され、場合によっては罰則が適用されます。
「発覚しないのでは」と楽観視する人は見受けられますが、調査によって多くの事業者が指摘されている状況です。
もし、助成金を不正受給してしまうとどうなるのか、該当する行為や処分、罰則について解説します。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度は?
目次
助成金の不正受給とは
助成金の不正受給とは、虚偽の申請や不正な手段を用いて、本来受給資格のない助成金を受け取る行為です。
架空の経費を計上したり、二重申請したりするなど、いくつもの行為が該当します。
不正受給が発覚した場合、受け取った助成金の全額返還が求められ、速やかに返還しなければなりません。
さらに、悪質な場合は刑事告発されることもあり、社会的信用を失うことにもつながります。
不正受給を防ぐためには、申請前に公募要項を正確に理解し、適正な使用と正確な報告を徹底することが重要です。
不正受給の事例
不正受給の事例は、以下が挙げられます。
- 雇用調整助成金:ある企業が全社休業として助成金を申請していた期間中、一部の従業員が実際には業務をおこなっていた。
- 人材開発支援助成金:教育訓練機関への費用を支払った直後に、同機関から企業へ資金が還流していた。
これらはほんの一例に過ぎませんが、さまざまな場面で不正受給が発生し、その後の調査によって返還命令が出されています。
助成金の不正受給に該当する行為
助成金の不正受給に該当する行為はいくつもあり、例を挙げると以下のとおりです。
虚偽申請や虚偽報告
助成金の不正受給には、虚偽申請や虚偽報告が含まれます。
主に、申請書類へ事実と異なる情報を記載して申請したり受給したりする行為です。
例えば「実際には存在しない事業内容を記載する」「従業員数や売上高を偽って報告する」などが考えられます。
また、申請時だけではなく、実施報告書に虚偽の成果を記載することも虚偽報告として不正受給の扱いです。
虚偽申請も虚偽報告も、意図的な詐欺行為と見なされ、発覚した場合は全額返還に加えて重いペナルティが課されます。
経費の架空計上や水増し
経費の架空計上や水増しも、不正受給の代表的な行為です。
例えば、実際には支出していない経費を計上したり、経費の金額を過大に報告したりすることで、補助金を多く受け取れるようにします。
具体的には、架空の取引先との請求書を作成したり、実際よりも高額な請求書を利用したりするなどです。
これらの行為は、助成金の不正受給であるだけでなく、会計不正にも該当するため、どちらの観点からもペナルティを受けてしまいます。
従業員の名義貸し
従業員の名義貸しは、助成金の対象人数を水増しする不正行為です。
例えば、実際に雇用していない従業員の名前を申請書に記載することが該当します。
また、在籍していない期間に給与を支払ったように装う手口も過去には存在しました。
名義貸しは雇用助成金の不正受給として扱われ、発覚した場合は重い罰則が科されます。
二重申請
二重申請とは、同一の経費や事業内容で複数の助成金を重複して申請・受給する行為を指します。
例えば、同じ設備投資に対して複数の補助金を申請したり、別の助成金制度を利用して重複して受給したりする行為などです。
基本的に助成金は同一の経費や事業に対して一度しか利用できず、意図的に申請した場合は詐欺と見なされかねません。
期限の未遵守
助成金には、使用期限や報告期限が設けられており、これを遵守しない場合は不正受給と見なされることがあります。
例えば、事業完了報告を遅延したり、成果物の提出期限を守らなかったりすると、不正と見なされる場合もあるかもしれません。
また、事業の開始日や終了日を偽って申告することも不正とされます。
助成金の不正受給が発覚した際の処分
助成金の不正受給が発覚した場合、いくつもの処分が科されます。
支給の取り消し
正当な申請ではないため、助成金の採択や支給が取り消されることは免れません。
申請内容が認められ支給が決定していたとしても、不正受給が発覚すれば、直ちに取り消されます。
ただ、申請する側が自分で誤りに気づいた場合は「取り下げ」の手続きを済ませることで、取り消し処分ではなくなります。
助成金の返還
既に、助成金の手続きが完了し受給している場合は、返還命令に応じなければなりません。
例えば、後から書類が改ざんされていることが判明した場合、返還命令が出されます。
期日までに変換しなければ、延滞金も加算されるため、速やかな対応が必要です。
5年間の助成金不支給
助成金の不正受給が発覚した後、5年間は助成金の申請や受給ができません。
不正受給の対象となった助成金だけではなく、関連する助成金の受給ができなくなってしまいます。
例えば、キャリアアップ助成金を不正受給した場合は、関連する雇用関連助成金がすべて受給できません。
また、新設される助成金にも申請できなくなるため、大きな損失を受ける可能性があります。
不正受給したものと並行して申請している助成金がある場合は、すべて受理されていないものとして扱われます。
事業者情報の公表
補助金を不正受給した事業者は、名称や所在地などの情報が公開されます。
誰でも閲覧できる情報であるため、社会的信用の失墜につながってしまうでしょう。
助成金を受給できないだけではなく、日頃の業務にも悪影響を与えると考えられます。
場合によっては、取引を停止されたり、融資を受ける際に影響したりするかもしれません。
助成金の不正受給に対する罰則
助成金の不正受給に対して直接取り締まる罰則は存在しません。
補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」によって、不正受給が禁止されていますが、助成金には同様の規則が存在しない状況です。
ただ、一般的には虚偽の内容で申請し、助成金の受給を目指すことから、詐欺罪が適用される傾向にあります。
詐欺罪だと判断された場合、罰則の上限は以下のとおりです。
- 懲役10年以下
- 罰金1000万円以下(法人の場合は3億円以下)
これらのどちらか、もしくは両方が科されるため、注意しなければなりません。
どちらも非常に厳しい罰則であり、不正受給は絶対に避けるべき行為であることを示しています。
助成金を不正受給してしまった際の相談先
何かしらの理由で助成金を不正受給してしまった場合は、速やかに相談することが重要です。
労働局
助成金は労働局が扱っていることが多いため、該当する労働局へ問い合わせ「どの助成金について、どのような状況で不正受給してしまったのか」について正直に伝えましょう。
伝えた内容を踏まえて、担当者が適切な対処方法を案内してくれるはずです。
自分から問い合わせすることで、状況を早急に改善できる可能性が高まります。
また、自己申告によって申請を取り下げ「誓約書」を提出できれば、厳しい罰則が適用される可能性を下げることが可能です。
弁護士事務所
悪質性が高いと判断される場合は、弁護士に相談することも重要です。
例えば、虚偽の内容で申請し、助成金を受け取っている場合は、刑事告発される可能性があります。
専門知識なく対応することは困難であるため、速やかに相談するようにしましょう。
仮に悪意がなくても、適切な対応を取らなければ刑事告発されるリスクがあるため、事前に弁護士へ相談することを視野に入れるべきです。
まとめ
助成金を不正受給してしまうと、返還命令や加算金、刑事罰などさまざまな罰則が適用されます。
そのため、意図的に不正受給しないことはもちろん、誤った手続きで不正受給にならないように考慮することも重要です。
もし、助成金の活用について不安がある場合は、F&M Clubの活用がおすすめです。
F&M Clubは中小企業のバックオフィス業務をサポートし、助成金の活用サポート範囲に含まれています。
助成金の情報提供など、幅広い支援が可能であるため、ぜひ、F&M Clubの活用をご検討ください。